1920年代(大正4年)に二股ソケットや電気アイロン、扇風機が登場して日本の家電元年が始まり、50年には白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫の「三種の神器」の普及が始まりました。
60年には電子レンジ、カラーテレビへと家庭の電化製品が豊かな暮らしを演出します。
1970年(昭和45年)、わが社が創業し技術革新の波に乗り日本経済の成長を支えていくことになりました。家電100年の進化のなかで、2000年代に「新、三種の神器」、デジタルカメラ、DVDレコーダー、薄型テレビが登場し生活スタイルの多様化に家電も対応してきましたが、2017年代に入り総合家電メーカーは一社になってしまいました。その家電メーカーも自動車部品の製造など家電以外の比率を高めています。家電というジャンルから新たな、あらゆるものをネットにつなぐ「IoT」「AI」の技術を駆使した進化をみせています。2020年、創業半世紀を迎えるわが社は未来を支える新技術で応援してまいります。
人口減をカバーし「新3K」をもたらすロボット
東京オリンピックの特需が終わりに近づく建設業では、建設技能労働者が2025年には2014年の342万人から216万人に減ると計算しています。今後、インフラの回収などが増えると考慮し約350万人が必要になるが、新たに就職する人では補いきれない35万人分の働きをロボットを活用してまかなうとして、すでに積極的な活用が始まっています。
資材を自動で運ぶ搬送ロボットや鉄骨を溶接して柱をつくるロボット、床のコンクリートをコテでならす仕上を担うロボット、重い材料などを持ち上げる時に作業員の腰の負担を軽減するロボットスーツなどが活用されています。かつて建設現場は「きつい、汚い、危険」の3Kの代表格とされていましたが、これからはロボットの活用によって人は複雑な作業に注力し、魅力ある職場に転化すれば高い「給料」、長い「休日」、「希望」がもてる“新3K”に変わると期待されています。当社も新しい技術で支援してまいります。
素敵な「おもちゃドクター」との出会い
「おもちゃドクター」三浦康夫さん(71)の話に出会いました。
三浦さんは子どもの頃、おもちゃで遊ぶより「どういう仕組みで動いているのか」に興味を惹かれ、おもちゃを分解して遊んだ方で大学も工学部に進み、仕事も自動車メーカーの技術者として40年以上、エンジンの設計に携わり、その後「おもちゃドクター」として「おもちゃ病院」を開設されたそうです。
「治せなかった患者さんはほとんどいません」と、自作の工具を駆使して月の半分以上はおもちゃドクターとして過ごされています。
治療の終わったおもちゃを手渡した時の子供の笑顔を見るのが楽しいと語っておられますが、私たちの手作りした製品をお客様に手渡しするときは、三浦さんと同じような嬉しさを感じます。
「好きなことで喜ばれる、こんな幸せはないですね」と語る三浦さんに、ともにエンジニア魂を見た気がします。
科学立国は「リケジョ」から
“リケジョ” 理工系女子と呼ばれて話題になりましたが、どうやら科学技術立国ニッポンの復活の鍵は女子中高生にあるようです。
現在のIT技術者に占める女性の割合は13%程で、内閣府も女性の研究者の割合が米国の半分以下だとして力を入れています。
特に女性が少ない分野は科学、技術、工学、数学で英語の頭文字から「STEM(ステム)」と呼ばれ、日本は他国と比べてステムの分野に進む人の男女比に不均衡があると指摘されています。そこで、女子学生が理工系の職場見学や仕事体験をする「理工チャレンジ」の実施や、筑波大学の2泊3日の「リケジョサイエンス合宿」が開催され、中高生約100人が参加したり、東京理科大でも「科学のマドンナ」と題して理系出身者を招いての講演会などを開いています。リケジョのノーベル受賞者も夢ではなさそうです。
技術進歩と机の下開発魂
ソニー用語に「机の下開発」という言葉があるそうです。有志の技術者たちが空き時間を使って試作機器や得意の技術を伸ばす技術開発のことで、12年前に生産終了したソニーのイヌ型ロボット「aibo」を復活させ、戌年の今年1月に発売、ブームになっています。
ホンダの発明大会も技術者魂に挑戦するコンテストで話題ですが、我が社にも「机の下開発魂」があり、世に送り出した製品もあります。作業の油汚れ洗浄から生れた石鹸「クオリオ」や爪をやさしく研ぐ「爪みがき」等です。
一時はロボット開発から撤退したソニーですが、技術者は終了後も画像や音声認識、力を制御する技術を密かに研き、いま生かせる技術を総動員してAI搭載の2代目「aibo」で“ロボットで人々の生活をより刺激的に、豊かにしたい。アイボの復活は我々の挑戦のスタートにすぎない”と語っています。成長とは変革の大切さですね。
進化する素粒子研究の地「スーパーカミオカンデ」
岐阜県飛騨市は、我が社の渡辺創業社長の故郷で飛騨工場もある地です。
2015年に東京大宇宙線研究所の梶田隆章所長がノーベル物理学賞を受賞して有名になった、素粒子ニュートリノの観測装置「スーパーカミオカンデ」で注目されました。飛騨市の旧神岡鉱山の地下にある鉱道を活用した施設で、研究チームが新たに、はるか遠くの宇宙で起きた超新星爆発から放出された反電子ニュートリノの新しい観測装置の開発に取り組んでいます。装置の感度を上げるため、レアアースのカドリニウムを水槽内の水に0.1%混ぜることで飛来したニュートリノを観測する計画で、2019年度にも稼働させるそうです。
銀河系のはるかかなたから来る素粒子を正確に観測できれば、超新星爆発の歴史を解明し宇宙だけではなく、物質の成り立ちの解明にもつながると期待されています。
この世界初の研究も次のノーベル賞に輝く、飛騨の誇りに思えてなりません。
“なぜ”が科学技術発展の芽!
世界で活躍する科学者や技術者をめざす高校生が研究成果を競う「第15回高校生科学技術チャレンジ」の発表がありました。
全国105校から174研究の応募があり、最終審査の対象となった13分野、30研究(個人10、チーム20)が選ばれ、文部科学大臣賞などの各賞に挑戦しました。“どんな着想から研究に入り、どこまで研究をし、この先どんな展開を考えているのか”そんなポイントで審査されたユニークな研究が受賞しました。
「なぜアサガオの花は朝に咲くのか」の解明、「絶滅危惧種のカスミサンショウウオが、どこに生息しているのか」や「木の廃材を活用し、野生のツツジの花酵母からバイオエタノールを生産」、「こんにゃくから高機能シルクの創出」などユニークな研究成果が発表され、5月に国際学生科学技術フェアにも出場する研究もあり、発明や解明の瞬間に生れる感動は科学技術発展の第一歩です。我が社に訪れる高校生たちにも、そんな輝きがあります。
貼る太陽電池の誕生
震災による原発事故以来、自然エネルギーや再生可能なエネルギーを模索する研究が加速しています。太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスに始まり潮流、波力、浮力、海洋温度差発電等々、可能な限りの電力開発の研究が進んでいます。
理化学研究所と東京大学の研究チームが“衣服に貼れる太陽電池”を開発したと英科学誌ネイチャー・エナジーに発表しました。
原理は、有機化合物を極薄の高分子膜上に塗りつけて厚さがわずか3マイクロメートルの太陽電池を作成したとのこと。伸縮性があり曲げたり押しつぶしたりしても正常に作動するため洗濯もできる超薄型の太陽電池です。
シャツなどに貼り付け、血圧や体温を常に測定して病気を早期発見する医療器具や、衣服と一体化した薄型スマートフォンなどの電源に使えるし、ウエアラブル(身につけられる)機器の電源としても応用できると期待されています。
過酷な月面に挑戦する日本の技術
世界初の月面探査レースが米、グーグルがスポンサーでXプライズ財団が主催し、今年中に探査車を打ち上げ、月面で500m移動させ画像を最も早く地球に送ったチームが優勝するというレースです。
現在、5チームが参加するそうで日本からはHAKUTO(ハクト)チームが過酷な環境に耐えられる技術力を結集して、九州工業大学・超小型衛星試験センターで取り組んでいます。
月面は太陽光が当たる部分では100度、日陰では零下百数十度になるため様々な耐熱対策の試験が必要です。
探査車の名前は「SORATO」で、漢字では「宙(そら)兎(と)」、月の兎をイメージした名前です。
12月28日にインドのロケットに共同で打ち上げられ、1月末に月に着陸する予定だそうです。重さ4k、長さ58㎝、幅54㎝、高さ36㎝の小さな国産探査車に期待がかかります。
優勝賞金2000万ドル、23億円だそうですから、頑張ってほしいですね。
今年の「未来技術遺産」は。
2008年から始まった科学技術の歴史上重要な成果として保存する、重要科学技術史資料(未来技術遺産)が今年も15件登録されました。
1968年に発売され、ハイビジョンテレビが普及する先駆となったソニーのトリニトロンカラーテレビが登録されました。また、産業技術総合研究所と川田工業(現、カワダロボティクス)が、2003年に開発した二足歩行ができる人間型ロボット「HRP-2プロメテ」が人間と協働できるロボットの先駆けとなったとして登録されています。
1989年に登場した富士フイルムのカラーネガフィルム「フジカラーリアラ」が従来のフィルムに4つ目の層を導入した鮮明な色彩を再現したとして登録されたのですが、デジタル映像の今、30年一昔とはいえ“技術遺産”なのですね。今年ですでに240件が登録されたそうですが、こうした技術を基礎に新しい技術が誕生していくのですから、まさに“日進月歩”ですね。

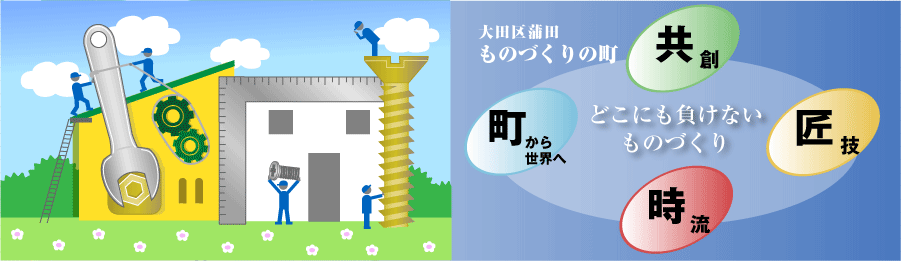
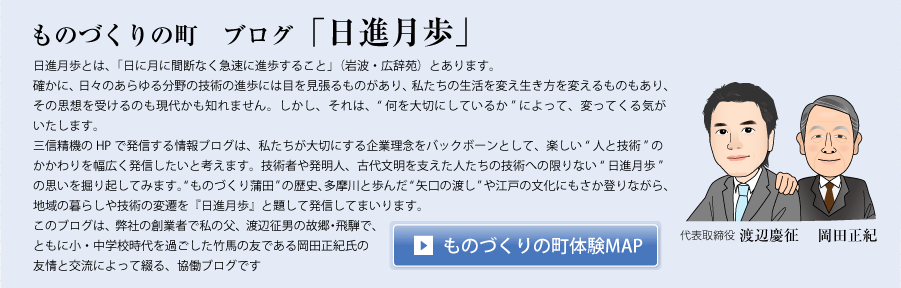
アーカイブ