平成の30年間が終わり新しい時代へ向けて総括をすると、「JAPAN as NO.1」への“おごり”がその後の「失われた10年、20年」の低迷につながり、イノベーション的挑戦の阻害要素になったと言われています。
科学技術には大きな変化や進歩があげられますが課題も見えてきます。
この間のノーベル賞受賞者は18人で欧米に集中する中で存在感を示しますが、研究費の削減などで基礎研究力の低下が懸念されます。
生命科学や医療の分野では臓器移植や脳死移植、IPS細胞など技術革新が相次ぎました。一方で、雲仙普賢岳の大火砕流、淡路大震災、東日本大震災の自然災害に加え原発が地震と津波に襲われ、科学技術の功罪が問われています。パソコンの普及によりネット社会の到来で時代の変化は一変しました。IT化やIOT、AIなど科学技術の急速な進歩は次の時代にどのようなイノベーションをもたらすのか、倫理が問われます。
「AI」と「EI」の進歩
人工知能・AI (Artificial Intelligence)は、様々のものに組み込まれ科学技術の発展に新しい革命をもたらしていますが、一方で人工知能が人間を凌駕するのではないかという不安があることもたしかです。
急速な「AI」の普及のなかで、感情的知性と表現される「EI」(Emotional Intelligence)が話題となっています。EIを簡単に言えば“感性”です。
AIは総てを記憶させプログラムされた知能ですが、人工知能に人間と同じ感情で笑わせることはとても難しいそうです。AIのスピード、利便性は大きな利点ですがEIの根源は、一人ひとりが持つ “好奇心”や “尊重の精神”、 “共感力”などの意思をベースに創り上げる社会的存在価値です。
「AI」の進歩は「EI」の発想が源であり人間の“感性”を大切にした科学技術の進歩であるべきだと考えています。
人と一緒に働くロボットたち
Iot社会の実現が急速に広がっています。
便利さだけではない、社会環境の変化に対応したロボットたちの働きが頼もしい限りです。
■障がい者や外出困難者の社会進出を支援するロボットでは遠隔操作で接客ができる“分身ロボット”が活躍しています。
■薬剤師の代わりに薬の処方箋データを入力すると棚から薬を選んだり、複数の薬を一つの袋にまとめ正確に処方してくれます。
■未来レストランでは、料理ロボットが炒めて、揚げて、運ぶ手際よさで人手不足や衛生面でも最近のバイトテロの防止にも、こうした自動化は必要かもしれません。
■農業や林業分野では“獣害対策ロボット”が活躍しています。イノシシやシカを自動ロボが追い払ったり、捕獲状況を監視したりと広がっています。
労働人口の減少や後継者不足に悩む現場でIotやAI化は進みますが、人とコミュニケーションのできるロボットが求められています。
大阪万博とともに
約50年前、1970年(昭和45年)に史上最大の規模で開催された大阪万博は、「人類の進歩と調和」をテーマに最先端の技術を集め、海外参加76ヵ国、国内32団体の参加で開催さえました。
183日で入場者6421万人、1日平均35万人の入場者に心躍る未来技術を見せてくれました。
今では当たり前になった駅の自動改札機や動く歩道「トラベーター」やガラス張りの噴流式洗濯機の技術を使った人間洗濯機が話題でしたが、超音波で汚れを落とす洗浄器や介護用の入浴槽へと発展しています。
2025年に大阪で2度目の世界万博が決まり、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、多様で心身ともに健康な生き方、持続可能な社会、経済システムを目指して開催されます。
昭和45年、大阪万博の年に誕生したわが社も科学技術の進歩とともに次の半世紀を迎えます。IotやAIの進化を見極めながら健康経済社会の発展に寄与してまいります。
多機能化する自販機
どこにでもある便利な自販機ですが設置場所が飽和状態で、年率1%前後の台数減が続いているそうです。
17年度の普及台数は489万2000台、18年度は484万台となっています。自販機の大多数を占めるのは清涼飲料ですが、ちょっと変わり種のアイデア自販機が広がっています。
焼きたてのピザやクレープ、だしスープ缶。
奈良県大和郡山市には生きている金魚を売る自販機も登場。他にも金貨や銀貨が買える自販機、巨大な買い物では車を売る自販機ビル。ミネソタ州では雪合戦の「雪玉」を売る自販機もあるそうですから、?という感じです。戸外に設置された自販機を外国人は金庫が外に置いてあると思ったとか。そんな自販機に防犯カメラが内蔵されたり、災害時に無料になったり傘の無料貸し出しで地域貢献をする「レンタルアンブレラ」あり、Lot社会とともにますます自販機の多機能化が進みそうです。
たよりない“弱いロボット”づくり
AI(人工知能)が広がりIot(モノのインターネット)化が急速に進んでいます。
そんな世の中で、あえて“たよりないロボット”をつくる技術者が話題になっています。
豊橋技術科学大学の岡田教授で、人と機械が交感できる“弱いロボット”を世に出してい
ます。
その理由は、あえて弱点や限界をさらすことで接する人の助力を引き出すことができるか
ら“人の情動に訴えかける弱さが新しい力を生み出せる”と説いておられます。
昔話ロボットは、たどたどしい話しぶりに子供たちが助け舟を出すそうです。たよりない
ロボットはかえって人間を勇気づけ、心のなかから人間の力や能力を引き出し、エデュケ
ーション「内から引き出す」という教育本来の働きをしてくれるように思えます。
産業用ロボットでは、そうもいかないでしょうが接する人の力を引き出すロボットには、
効率優先が求められる技術にない斬新な発想と多様性を示唆しているように思われます。
宇宙へ飛び出す「サラリーマン衛星」
蒲田の下町工場がモデルの「下町ロケット」のTVドラマの続編が始まって、また注目を集めています。2014年12月に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ2」が長い旅をして小惑星リュウグウに来年早々、着陸予定で宇宙への関心が高まっています。
「はやぶさ2」が旅に出たその年、新橋の居酒屋で宇宙好きの3人のサラリーマンが宇宙開発の夢を語り「自分たちの衛星を打ち上げよう」と、会社員や学生たち350人で「リーマンサットスペーシズ」を立ち上げ、“サラリーマンによるサラリーマンのための民間宇宙開発”に挑戦しています。お金も知識もないところから2年弱かけて、重さ約1キロの超小型衛星をH2Bロケットで種子島宇宙センターから国際宇宙ステーションに運び来年3月までに、地球を撮影したり一般の人からのメッセージなど6千通を地上に送ったりするそうです。酒場で語ったサラリーマンの夢が実現する時代、ロマンを感じますね。
IOT時代がやってくる!「熱中症予防シャツ」
地球温暖化のせいでしょうか今年の異常気象にとまどいます。豪雨、突風、落雷、高潮、集中する台風の襲来、なかでも各地で40度を超える気温が連続し「熱中症」被害が広がり、その対策が急がれています。
今、NTTとアシックスが熱中症を予防するセンサー付きのシャツを開発しています。
着ると服の中の温度などをスマートフォンが把握し熱中症の危険度を確認し予防するというシステムです。
屋外で長時間仕事をする人やスポーツをする人、屋内でも熱中症になりやすい病院や介護施設、熱中症になりやすい高齢者への利用を想定しているとのことですので頼もしい味方です。
国も東京オリンピックに向けて“暑さ対策”をハード&ソフトを含め考えていますが、いよいよIOT(物とインターネットの繋がり)によるデジタル社会の実現が加速されそうです。「サマータイム」も始まるのでしょうか―。
「昔の名前」で“進化”しています。
エポック社の「野球盤」の初代は、1958年に木製で発売され遊んだ方も多いかと思いますが、発売60周年を記念した70代目の新作「3Dエース モンスターコントロール」が進化して発売されました。磁石を使った変化球、消える魔球や放物線を描いてスタンドに飛び込む本塁打を打てると進化し70代目は、内角高めを狙えたり、球速やコースを表示する電光掲示板付きと進化して登場です。
もう一つは、ソニーのロボット犬「aibo」で2006年には一旦生産を終了しましたが今年の1月に復活し「机の下開発魂」として注目されましたが、人工知能(AI)を搭載して発売され日本では2万台越を販売済ですが、世界でも販売されます。
“飼い主の表情や発言、触り方などを自ら分析して感情をあらわす機能つき”で、体も丸みを帯び瞳が動く新型に衣替えしての登場です。見本市では「キュート」と好感触だそうです。“昔の名前”も時代の波でしょうか。
食料品加工の新しい働き手!
人口減による人手不足は、産業界にとって深刻な要因ですが、単純労働をロボットに任せ限られた人手を付加価値の高い仕事に回そうと、自動化の技術進化が始まっています。
産業用ロボットの出荷先は、半導体などの電気機械が40%、自動車が30%を占めますが食品加工分野にも広がっています。この分野はまだ2%程ですが、わが社でも進出しています。産業ロボットは、技術進化と人手不足が普及の後押しをしてくれています。
すでに稼働しているジャガイモの有毒な芽を取り除くロボットは、1個あたりの作業時間は2秒でフライドポテトやサラダなどの加工現場で活用されています。
北海道では水産加工場でホタテの殻をロボットでこじ開け貝柱を切り取る作業では、1分あたり90杯で手慣れた従業員11人分の働きですから、高齢化や人手不足の現場ではなくてはならない新時代の“従業員”の役割を担っています。

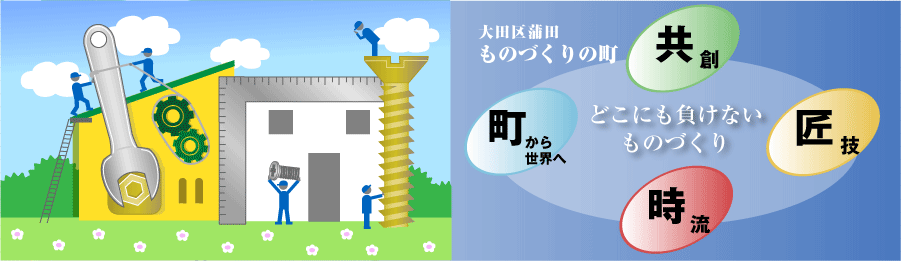
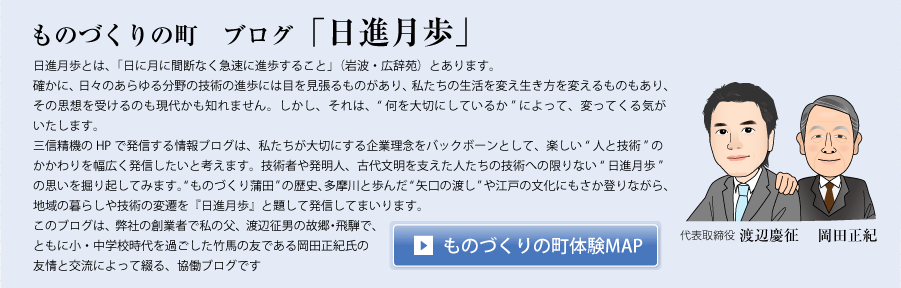
アーカイブ