ミステリアスな名称ですが「都市鉱山」の名付け親は東北大学の南条道夫教授で、「工業製品を再生可能な資源とみなし、蓄積された場所を都市鉱山と名付けた」と88年に論文で発表したのが最初だそうです。
携帯電話やパソコンに使われる希少金属(レアメタル)が再利用の対象で、インジウムやパラジウム、コバルトや金、銀、錫、アンチモンなどの金属が回収されています。日本国内にあるインジウムの量は、世界の天然鉱山にある埋蔵量の6割あり、世界の消費量と比べると3.8年分に当ると推測されています。また携帯電話1台に使われる金の量は6.8mgで、鉱石より含有率が高く、その埋蔵量は6,800tで、時価22兆円相当に上るそうですからお宝鉱床です。こうした有用金属を含む製品の廃棄物や製造中にでる廃物の再利用回収システムを作る「人口鉱床」計画も進められており、私たちも希少金属資源のリサイクルには細心の注意を払っています。
「手」の国、日本
私たちの工場は、お客様と話し合いながらどこにもない誰も作った事のない精密機器や実験機器を手づくりで研究開発をしています。蒲田にある多くの工場は熟練の職人達の手仕事に、世界が高い評価をしています。まさに、日本は”手の国”だと思っています。
土と炎の詩人で陶芸家の河井憲次郎は、陶芸を「手考足思」、「手念足願」、「手護足解」と表現しています。「上手」、「下手」は手の技を語り、「手本」、「手柄を立てる」は手を褒め、「手腕」は力量、「腕利・腕前」も手から生まれた言葉です。手が機械と異なるのは、いつも心とつながっていてものを創らせ、高め働きに悦びを与えていることです。手が働かなくなると「手詰り、手遅れ」となり、結果は「手ぬかり、手落」と厳しい表現になります。この手の仕事の力が衰えたら日本人は特色の乏しい国になるのではないでしょうか。いつも、我が手を見ながら改めて「手」に感謝しています。
ロボットと暮らす日
日本の総人口は2040年度頃には1億人を割り、9,600万人程になり生産労働人口は8,000万人から30%減の5,600万人になると予測されています。この人口減をどのようにカバーすれば良いのでしょうか。
さて、現在様々な分野でロボットが活躍しています。家庭ではお掃除ロボットや、人工知能を使って会話をしたり接客をする人型ロボットが働いています。すでに工場では多くの工業用ロボットが活躍していますが、医療分野や介護施設でもロボットが進出しています。15年後の2030年には現在の仕事の30%~40%がロボットに代わっていると予測されていますので、生産労働人口減をロボットがカバーすることになるでしょう。もちろんロボットは万能ではありませんが、鉄腕アトムやドラえもん、ケアロボット、ベイマックスのようなマンガやアニメの世界が実現するかも知れません。我が社も工業用ロボットの一翼を担っていますが、ロボットと暮らす日を想像しています。
地域の魅力を発信する”町工場・オープンファクトリー”
ノーベル賞の受賞者を祝う晩餐会で使われたナイフやスプーン、フォームなどの美しいテーブルウェアが新潟・三条の町工場で作られたことで話題になりましたが、いま地域にある町工場の魅力が地域活性化に一役かっています。大田区でも「おおたオープンファクトリー」として、世界に通用する職人技を見学したり、体験したりできる工場が公開されています。工場の得意な技術は持ち回りでこなして製品を完成させる「仲間回し」の連携プレーの見学やミニフライパン作りを熟練の職人に教わりながらステンレス板の加工をしたり、取っ手やプラスチックカバーの製作などの体験を楽しめるのです。町工場の職人技を間近に見られるオープンファクトリーに、海外からの弟子入りもあり人気の場となっています。台東区の「モノマチ」や「A-ROUND(エーラウンド)」、墨田区の「スミファ」などのオープン町工場もあり、地域と共生しながら新しい町の魅力を発信しています。
日進月歩の夢を乗せて「はやぶさ2」 の旅立ち
小惑星イトカワから微粒子を地球に持ち帰った小惑星探査機「はやぶさ」の感動と夢を受け継ぎ、「はやぶさ2」が地球と火星の近くを回る小惑星「1999JU3」 に向って、12月3日種子島宇宙センターから旅立ちました。
「はやぶさ2」 は、ほぼ1号と同じ大きさですが重さは少し重い600kgで、姿勢制御装置やイオンエンジンの耐久性や推力を増強するなどの技術的な改良を重ねて飛び立ちます。大手企業から数人の町工場まで100社以上の職人達の夢と技術を乗せ、小惑星に到達するのは2018年 夏の予定で小惑星の表面物質や地下物質を採取して地球に戻るのは、2020年東京オリンピックの年の年末になるそうです。こうした探査機の実験はやがて火星に人を送り100年後かもしれませんが、火星移住を目指すことが目標だそうですから宇宙へのロマンは広がります。我が社も日々 の技術革新が常に夢への挑戦ですが、「はやぶさ2」の成功を願わずにはいられません。
三人のノーベル物理学の受賞に思うこと
今年のノーベル物理学賞に青色LEDの発明・普及で、赤崎、天野、中村三教授が受賞されました。その理由は「明るく省エネルギーな白色光を可能にした効率的な青色発光ダイオードの発明」で、青色LEDは「人類に最大の恩恵をもたらした発明」とたたえています。
赤崎先生(85歳)は「私は幸運で、決して私ひとりでできたわけではない。」
闘う研究者として知られる中村先生(60歳)は「自分の発明したものが使われていることは非常にうれしい。」
天野先生(54歳)は「私は平均的な学生だったが、一つのこと集中して続けること、人の役に立つことができると身をもって示すことができました。何をやるかを決めたら、必ずできるはずと思いこむことが大事」
と語っておられます。
21世紀を照らす光、LEDは私たちの生活を進化させる発明として広がりを見せることでしょう。受賞の言葉を聞きながら、「努力なしでは運は訪れない。努力は人を裏切らない」ということをもう一度、思い起こしています。受賞、おめでとうございます。
温故知新と機械遺産
群馬県富岡市の「富岡製糸場」がユネスコの世界文化遺産に登録され、連日にぎわっているそうです。明治5年に操業を始め、外国の機械や指導者も入れて最新の技術を融合した模範工場でしたが、昭和62年操業を停止し以来、機械や建物が取り壊すこともなく管理してきた結果の世界文化遺産です。当社の古川工場である飛騨市には、製糸場で働いた女性の姿をまとめた「あゝ野麦峠」(山本茂実1968年刊)に、働きに出る女性たちが最後に泊る宿が描かれていますが今も昔の姿で営業しています。
日本機械学会が2007年から始めた「機械遺産」が毎年認定され、すでに69件が登録されています。南極で活躍した雪上車や現存最古の動力旋盤、黎明期の家庭用電化機器や農業機械、豊島園の回転木馬「カルーセル エルドラド」など日本の得意分野が見えてきます。日本の近代化の発展の証しとしての機械遺産は、蒲田の匠たちの歴史のようにも思えます。技術の日進月歩が「遺産」となることに感無量です。
筆記用ペンのミニ歴史
充填技術は我が社の専門技術の一つで、化粧品や食品、筆記具など様々な分野を手がけています。油性ボールペンは71年前の1943年、ハンガリーでラディスチオ・ピロによって開発され世界に広がりました。その後、水性やゲルインキボールペンなどが日本で開発・発売されています。古代の筆記用具は、アシの茎を使ったのが最初で、古代エジプトではペルシヤの沼地に成育したアシを3月に刈り、6か月間程ねかせて美しい光沢や黄色や黒色のまじった、あでやかな色を出す最高のペンを作ったそうです。アシの次には鳥の羽を使った羽根ペンが登場し、鷲鳥や白鳥、梟や孔雀、ペリカンなどの羽が使われています。その後ペンは金属に変わり、鋼や真鍮、金などが使われ、ペン先には耐久性のあるイリジウムやオスミニウムが使われた”万年筆”が誕生します。
一本のペンにも発展の歴史と進歩、そして技術の宇宙が詰まっているのが見えてきます。
まち工場の石鹸
現場で手についた油を落とすのが一苦労で、先代の渡辺が手荒れをせず油汚れを落とす石鹸を求めて開発したのが「ハネダクオリオ石鹸」です。
現場の悩みから生まれた石鹸の歴史をたどると、紀元前58年~52年のローマ時代にガリア人(現在のフランス)が、山羊の脂肪とブナの木の灰から石鹸を発明したと言われています。石鹸はSapoと呼ばれ、ドイツ語のSepeが語源で現在のSAVON(仏)になったのでしょうか。ラテン語の本では石鹸は牛、山羊や羊の脂肪と生石灰より強められた灰汁との混合物から作られ、イタリアや東洋ではシャボン草の根に石鹸質の液汁を含んでおり着物や毛織物を洗濯するのに用いられたと書かれています。また、酸性白土が「布さらし職人の白い粉」として使われ、国の名前を付けた「キオス島の土」、「サモスの土」と呼ばれ「襟洗濯用の土」もあり、土の色によって「黄色い石鹸」や「黒い石鹸」、「褐色の石鹸」と呼ばれていたそうです。なぜか、シャボン玉の夢が広がりそうな気がします。
科学と技術の協働
米デュークス大学教授ヘンリー・ペトロスキー著「エンジニアリングの真髄」(安原和貝訳・筑摩書房刊)を東京大学教授・佐倉統先生が書評を書かれていました。「科学は、自然の謎を解明する”知る”活動だ。対する技術(エンジアリング)は、何らかの問題を解決する営み。そのための便利な道具や解法を”作る”ことである。環境問題やエネルギー問題など、現代の難問を打破するためには、しばしば”科学的方法”が重要とされるが、大事なのは現実解を見つけるエンジニアリング的発想と方法である」と、科学と技術の違いについて紹介されています。
科学が上位で技術は格下と思われてばかりとか、基礎研究から応用研究と直線的に進むものではないとも論じています。本書の副題は”なぜ科学だけでは地球規模の危機を解決できないのか”とあるように、私たちの小さな商品開発も常に科学を技術で裏打ちし、技術を科学で実証する作業の連続で、示唆に富んだ指摘だと思っています。


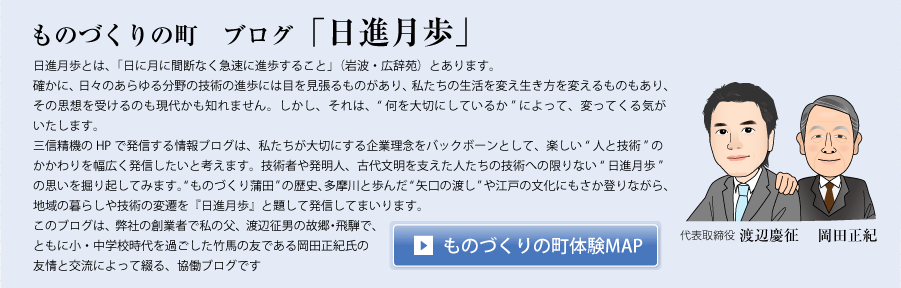
アーカイブ